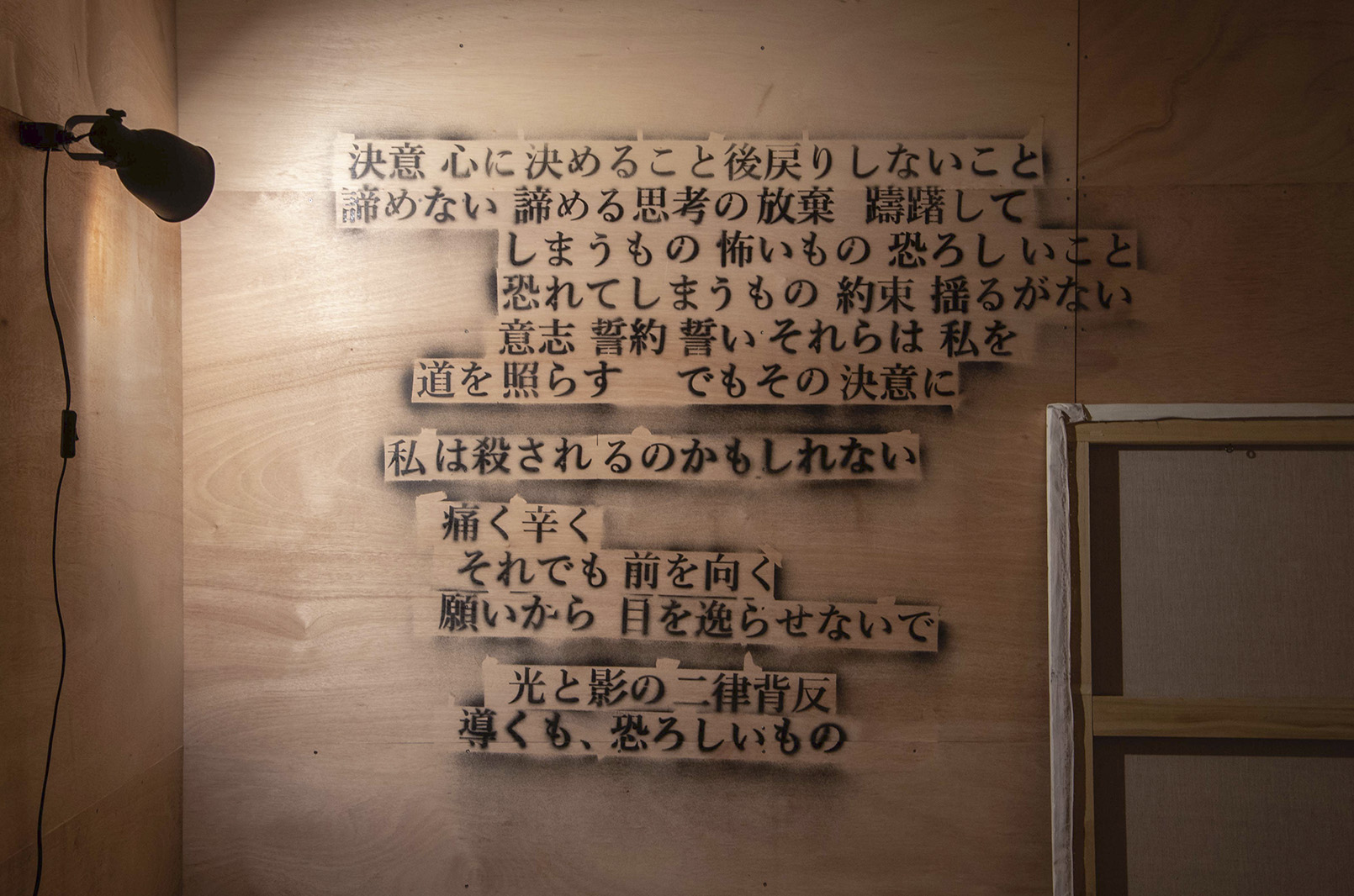言葉は思考の足場である。人は言葉を頼りに歩いてきた。もし、言葉を見つけられなければ天地も前後もわからぬ真っ黒の闇の中、頼りにする目印ひとつ定められず、すぐにその狂気に呑まれてしまったことだろう。しかし、言葉はまた枷でもある。誰かを呼ぶ名や軽はずみに暗闇に渡す言葉の所感に認識や感情、行動までもが囚われるようだ。
前は今もなお知れずいるのに、時間の不可逆性のみを拠り所に、過去に居ただけの場所を後ろとした。まるで、そこから離れたいかのように。前に進むためだけに後ろと定義されたような過去から、臆病者は一歩、歩を進めるごとに振り返っては後ろを確認している。「ああ、いくらか離れることができただろうか」あるいは「ああ、こんなにも離れてしまった」と。成長せねばと言わしめておいて誰もが過去に執着している。
きっと誰も本当に辿り着くべき先など持ち合わせてはいないのだ。何度も過去を振り返り、何度も何度も確認してはその光景を脳裏に焼き付け、しまいには戻りたいとさえ言い始める。やはり、過去も枷のようである。
とある部屋に、隠れ場とも言える押し入れがあった。これは誰かの原風景である。その者は幼い日の夜、その押し入れの中からカーテンに写る不気味な人影をみた。そして、彼は最近になって、また同じような体験をしたのである。あらゆる考え事、悩みの度に、自分の心の中にチラつく自分とは違う存在を。